第26回 イギリスへ再び―レイクフォーレストから羽ばたく―
時の流れ
会議の開催された会場は企業の施設であった。初日のランチ風景(図4)では,「久しぶり」あるいは「初めまして」のにぎやかな交流の場となった。
9年のブランクは新しい世代の出現と世代交代を実感させられる会議でもあった。新顔の参加者の1人に,オーストラリアの芸術系のドクターコースの学生がいた。彼女の名前はMartina Mrongovius。このシンポジウムの数年後,彼女から自宅に突然電話がかかってきた。「今,日本に来ている。東工大のホログラムを見学したいが,会えるだろうか」という内容だった。とりあえず急ぎ予定を調節して大岡山と田町に案内した(これらの作品については,後に触れることにする)。案内後,日本文化を味わってもらおうと居酒屋に誘ったら,このまますぐ大阪に戻ると言う。東京への日帰り旅行は,ただ石井のホログラム作品を見るためだけの目的であったことを知り,フットワークの軽さとホログラフィー愛に,関心と感動を覚えた。さらに数年後,NYのHoloCenterの創設者Ana Maria Nicholsonがリタイアすると,彼女は若くしてディレクターとして,センターの活動を支える重要な人物となるのである。
ISDHには欠かすことのできない重鎮たち,Steve Bentonを2003年に見送り,この年の前年にはEmitt Leeth,さらに2か月前にYuri Nikolaevich Denisyukが逝ってしまった。最後のレイクフォーレストカレッジでのディナーパーティーでは,デニシュークの誕生日を祝ったことが思い出される。今,この原稿を書いている最中にも,痛ましいロシアのウクライナ侵攻のニュースが流れ続けている。あまりに胸が苦しくなる事態だ。キエフといえば,旧ソ連時代の1989年に開催された国際会議で訪れたことがある(本誌2019年3・4月号掲載)。デニシュークやベントン,そして多くの西側研究者も出席していた。キエフは歴史的建物の立ち並ぶ美しい街だ。今そこが理不尽な思考によって戦禍に曝されている。会議を主催したVladimir Malkovは当時キエフで教鞭をとっていたが,ソ連崩壊後はアメリカに移り研究を続けている。温和な人柄の心情はいかばかりか。デニシュークが生きていたら何と思うだろう(デニシューク自身も,旧ソ連時代,国の圧力で長い間不遇の環境に置かれていた)。理不尽な武力行使は人類の歴史にまた一つ汚点を残すことになった。
会議は彼らの追悼で始まった。デニシュークのポートレートが展示された(図5)。スクリーンに映し出されたスナップ写真(図6)の3人は,まさにディスプレイホログラフィーの“生みの親たち”である。
 これまで筆者の発表は,新しい制作活動の紹介といった類であったが,この回では趣向を変えることにした。ホログラム作品を作り続けてはや四半世紀が経過しようとしていた時期で,実は建物に常設として設置されていた作品たちに,社会環境の変化にともなう取り壊しや移転という事態が持ち上がってきたのである。そのころ,すでに複数の作品が新しい環境に移設されていた。シンポジウムの直前に再設置が完了した作品もあったことから,「アートホログラフィーの建築空間への応用とメンテナンス」と題して,移設時の作業の苦労や問題点を発表することにしたのだ。
これまで筆者の発表は,新しい制作活動の紹介といった類であったが,この回では趣向を変えることにした。ホログラム作品を作り続けてはや四半世紀が経過しようとしていた時期で,実は建物に常設として設置されていた作品たちに,社会環境の変化にともなう取り壊しや移転という事態が持ち上がってきたのである。そのころ,すでに複数の作品が新しい環境に移設されていた。シンポジウムの直前に再設置が完了した作品もあったことから,「アートホログラフィーの建築空間への応用とメンテナンス」と題して,移設時の作業の苦労や問題点を発表することにしたのだ。<次ページへ続く>









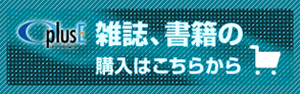
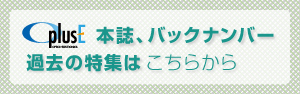

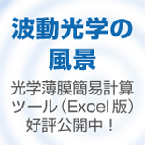







![研究室探訪vol.30 [奈良先端科学技術大学院大学 サイバネティクス・リアリティ工学研究室]](https://www.adcom-media.co.jp/wp-content/themes/adcom/scripts/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2022/11/laboratory1.jpg&w=80&h=100&zc=1&q=100)