ライバルとなる友を作ろう名古屋大学 産学官連携コーディネーター 虎澤 研示
光ディスクとともに部品事業を伸長
聞き手:本日はよろしくお願いします。早速ですが,ご経歴を見させていただきますと,ご出身は京都大学なのですね。 虎澤:ええ,京都大学の理学部卒業です。原子核物理を学んでいました。ちょうど学園紛争の盛んなころです。ですから,わたし自身,勉強らしい勉強はほとんどしなかったという状況でした。ただ当時は,「自主ゼミ」という勉強会が盛んで,学生たちが自主的に集まって勉強を続けていました。わたしは,専門の勉強よりも科学論などの哲学的な方面に興味を持っていました。「科学の発達が人間社会に課してきた役割とは何か? これから人間はどう科学と向き合うべきか?」というようなことなどを,少し批判的な目でとらえていました。
虎澤:ええ,京都大学の理学部卒業です。原子核物理を学んでいました。ちょうど学園紛争の盛んなころです。ですから,わたし自身,勉強らしい勉強はほとんどしなかったという状況でした。ただ当時は,「自主ゼミ」という勉強会が盛んで,学生たちが自主的に集まって勉強を続けていました。わたしは,専門の勉強よりも科学論などの哲学的な方面に興味を持っていました。「科学の発達が人間社会に課してきた役割とは何か? これから人間はどう科学と向き合うべきか?」というようなことなどを,少し批判的な目でとらえていました。聞き手:ご卒業後は三洋電機にご入社とのこと。どちらに配属されたのでしょうか?
虎澤:開発研究所というところです。当時,この研究所は岐阜に設立されたばかりで,新入社員としては第一期生になります。理学部出身だったので,最初は大阪にある中央研究所に配属されるかと思っていたのですが,予想に反して機器を開発する研究所に配属されてしまいました。あとから考えると,わたしが岐阜県出身なので岐阜にあるこの研究所に配属されたのではないかと思いました。三洋電機は大阪出身の人が大変多いので,なかなか岐阜県には来たがらないのですよ(笑)。
聞き手:開発研究所ではどのようなご研究をされたのですか?
虎澤:当時,ホログラフィーを利用して再生専用のビデオを作る「セレクタビジョン」というものがありました。米国のRCA社が音頭をとって,世界中の電機メーカーが開発を進めていた方式です。三洋電機ではプロジェクト形式で開発が進められ,わたしも10人ほどのメンバーの一人となりました。しかしこれがなかなかモノにならず,1973年ごろにプロジェクトが解散になってしまいました。それで,そこにかかわっていた技術者が今度は何をしていくかということになったわけです。候補に挙がったテーマの一つが光ディスクでした。オランダのフィリップス社が,「VLP(Video Long Play)」という光ディスクのコンセプトを提案したばかりで,各社がそこに飛びつき,早速,三洋電機でもその技術を開発することになったのです。わずか3人で開発のスタートを切りました。1974年ごろのことです。
 一方,当時は独テレフンケン社が開発した機械式のTED方式というビデオディスクの仕様がすでにあり,三洋電機はそちらの開発に力を入れていました。光ディスクは「よそもやっているからうちもやろう」という程度で,少人数で開始したわけです。その後,プロジェクトが潰されかけたりといろいろとあったのですが,世の中が光ディスクの方向に進み始めたので,なんとかやり続けることができました。1978年ごろにフィリップス社が提案したVLPが製品化され,そのあとに同社がコンパクトディスク(CD)の原型となるDAD(Digital Audio Disc)を提案しました。このころになると,技術者も強化されるようになりました。1979年ごろにはソニーとフィリップスが連合してCDを提案し,1982年11月に製品が発売されたと思います。
一方,当時は独テレフンケン社が開発した機械式のTED方式というビデオディスクの仕様がすでにあり,三洋電機はそちらの開発に力を入れていました。光ディスクは「よそもやっているからうちもやろう」という程度で,少人数で開始したわけです。その後,プロジェクトが潰されかけたりといろいろとあったのですが,世の中が光ディスクの方向に進み始めたので,なんとかやり続けることができました。1978年ごろにフィリップス社が提案したVLPが製品化され,そのあとに同社がコンパクトディスク(CD)の原型となるDAD(Digital Audio Disc)を提案しました。このころになると,技術者も強化されるようになりました。1979年ごろにはソニーとフィリップスが連合してCDを提案し,1982年11月に製品が発売されたと思います。わたしは主にピックアップなどを開発していて,それを事業部に移管したのがちょうどそのころになります。CDが発売され,研究所では「次に何をやっていこうか」という話になり,記録できるCDや書き換えできるCDが必要になるということで新たに開発を始めました。わたしたちが採用したのは光磁気方式でした。書き換えが何回もできることが選択の理由です。当時は記録できるディスクを作れる十分な技術や装置を持っていなかったので,ディスクについてはあるメーカーと共同開発しました。1984年にプロトタイプを発表したのですが,それが「世界初」の発表となって大きな話題となり,確かO plus E誌にも原稿を書いた覚えがあります。
聞き手:それがMO(Magneto-Optical disk:光磁気ディスク)の原型になるのですか?
 虎澤:そうです。そのころMOには二つの流れがありましたね。コンピューター向けのデータ用途と,音楽の記録などに使う消費者向けの流れです。三洋電機はデータ用途はあまり強くなく,消費者向けが得意でした。世の中の開発の主流はデータ用途で,われわれの開発方向はどちらかというと異端といえました。しかし,マスコミなどでも取り上げられ,「開発を強化しよう」ということになり,人員が少し増えました。1987年~88年になると技術的にレベルアップして,いよいよ実用開発という話になりました。ただ,民生用では規格が統一されないと実用化は難しいので,CDの規格を持っていたフィリップスやソニーに相談したこともあります。
虎澤:そうです。そのころMOには二つの流れがありましたね。コンピューター向けのデータ用途と,音楽の記録などに使う消費者向けの流れです。三洋電機はデータ用途はあまり強くなく,消費者向けが得意でした。世の中の開発の主流はデータ用途で,われわれの開発方向はどちらかというと異端といえました。しかし,マスコミなどでも取り上げられ,「開発を強化しよう」ということになり,人員が少し増えました。1987年~88年になると技術的にレベルアップして,いよいよ実用開発という話になりました。ただ,民生用では規格が統一されないと実用化は難しいので,CDの規格を持っていたフィリップスやソニーに相談したこともあります。1988年ごろに書き換え可能なCDの規格はできたのですが,商品化までには至りませんでした。著作権問題で暗礁に乗り上げてしまったためです。ダビングで子から孫へと音楽などが簡単にコピーされていったら,著作権団体としてはたまったものじゃないですからね。ただ,その技術を埋もれさせてしまうのは惜しいので,当時,ソニーが提案したのが,音楽の帯域圧縮の技術と光磁気の技術を組み合わせて直径64mmディスクに1時間以上の音楽を記録できるMD(MiniDisc)です。これが規格化され,1992年に発売されました。1995年ごろになると,今度はDVDの話が盛んになり,マネージャーとしてかかわったりもしています。
聞き手:そう言う点で言うと,確かに三洋電機は部品事業が強かった印象がありますね。
虎澤:当時,ピックアップやLSIなどの部品技術ではナンバーワンでした。非常に高いシェアを持っていて,今でもピックアップは市場の大きな部分を占めていると思います。CD-ROM用のLSIでも一時期,世界のシェアの70%ぐらいを占めたことがあります。光ディスクの機器開発の中で生まれてきたLSIをそのまま商品化して成功したのです。CD-R事業でも同様にエンコーダーLSI,ピックアップがシェアでナンバーワンになりました。
聞き手:消費者向け機器ではなかなか苦戦されていた覚えがありますが,性能の高さやコストが市場シェアを握る部品事業は大変強かったと思います。
大学では攻撃できる特許を取るべき
虎澤:記録メディアの部長をやったあと,今度はハイパーメディア研究所(のちのデジタルシステム研究所)の所長になりました。ここはマルチメディア関係の研究所で,記録メディアから放送メディア,通信から情報関係まで幅広い守備範囲を持つ研究所です。その後いろいろあって,2004年には三洋電機を退職し,名古屋工業大学に移りました。マルチメディア分野ばかりか会社全体のさまざまな技術分野に研究所長としてかかわったり,経営に携わることができたことは,その後,大学での業務に大いに役に立ちました。聞き手:大学でのお仕事はどのようなものだったのですか?
 虎澤:産学官連携関係です。大学に移った当時,全国の国立大学が法人化を控えており,このために産学官連携活動を進めるということで,各大学は企業経験者を採用したのです。わたしもその一環で大学に入りました。具体的には知的財産権に関する仕事ですね。2003年から大学知的財産本部整備事業というのが始まり,名工大では大学発のベンチャーとうまくドッキングさせて,大学の持つ知財を有効活用していこうという内容で応募して通ったため,人材を公募したのです。
虎澤:産学官連携関係です。大学に移った当時,全国の国立大学が法人化を控えており,このために産学官連携活動を進めるということで,各大学は企業経験者を採用したのです。わたしもその一環で大学に入りました。具体的には知的財産権に関する仕事ですね。2003年から大学知的財産本部整備事業というのが始まり,名工大では大学発のベンチャーとうまくドッキングさせて,大学の持つ知財を有効活用していこうという内容で応募して通ったため,人材を公募したのです。聞き手:大学が企業人を必要とした時期だったのですね。
虎澤:ええ。産学官連携という意味では,企業と大学との共同研究の推進などもテーマに挙がっていました。2004年ごろ,どこの大学でも共同研究センターや知的財産本部をはじめ,産学官連携に関する複数の組織を学内に持っていたのですが,いずれも組織が重たい割には少ない人数で頑張っているような状況でした。なかなかうまく横の連携が取れない実態に対して,名工大では機動力を発揮できるコンパクトな組織にまとめて機能的に動いていこうと組織改正を実施しました。2007年のことです。
聞き手:産学官連携センターのことですね。
虎澤:はい。そこで産学連携組織が再編され,その時にグループリーダーをやることになりました。共同研究を推進する部門,特許を扱う部門,大学発ベンチャーを扱う部門,そういう組織を一緒にした組織を作ったのです。この3月には定年を迎えまして,退職後の現在は,ここ(名古屋大学産学官連携推進本部)で非常勤でお手伝いさせていただいています。
聞き手:名古屋大学では,名工大と同じようなお仕事をされているのですか?
虎澤:そうですね。ここでは競争的資金――資金を獲得してくるような仕事をしています。ここも産学連携組織ですので,基本的にはやることは一緒ですね。
聞き手:競争的資金を獲得するために,大学間の連携は盛んですか?
虎澤:はい。例えば産学官連携分野においても,名工大に在籍中,共同で資金を獲得するために,文部科学省の知財ポートフォリオの形成事業に名大と共同で提案して採択されています。今後,大型の競争的な研究資金を獲得するためには,学内だけではなく学外との連携がより重要になってくると思います。
聞き手:わたしが学生のころは,大学で知財の話をあまり聞いた覚えがありませんが,今はだいぶ状況が変わったのですね。
虎澤:今でも,大学の知財というのは正直,非常に難しいものだと思います。なぜかと言うと,基本特許をどう取っていくかという難しさがあるからです。例えば,化学や薬学などの領域ですと物質そのものにかかわる基本特許は取れば非常に有効ですが,電気や自動車などの分野においては状況が異なります。また,多くの特許から製品が構成されています。こうした分野では,もし基本特許が取れたとしてもそれを回避できる特許が多く出てきます。そういう点で,大学がこのような分野で有効な特許を取るのはかなり難しいのではないかと思ったりもします。
もっと具体的に説明します。例えば特許対象として,ある3次元の組成の材料があったとします。A,B,Cという組成がX,Y,Zという比率で存在しているとします。そこでYとZを動かして「こんな特性が取れました」という発表をしますね。大学では,それをそのまま特許にします。でも,そこではXを変化させていません。一方,企業ではすぐにXを変化させた特許を出してきます。このように,大学の特許は「線」の状態で検討され,企業では「面」の状態で検討されることが多いのです。
聞き手:それは,検討する人数や資金の問題ということなのでしょうか?
 虎澤:それもありますが,もともと優れたデータを最初に発表することが大学の目的なので,そうしたことが起こるのです。それに対して企業は,実用や応用という観点でものを見て行きます。Xまで変化させて「面」にした段階で特許にして,その後に学会発表をします。物質そのものの特許ですと「発見した」以上にどうしようもないのですが,電気や自動車の世界では,構造や構成をこのように改良した程度ではなかなか特許取得にはつらいものがあります。
虎澤:それもありますが,もともと優れたデータを最初に発表することが大学の目的なので,そうしたことが起こるのです。それに対して企業は,実用や応用という観点でものを見て行きます。Xまで変化させて「面」にした段階で特許にして,その後に学会発表をします。物質そのものの特許ですと「発見した」以上にどうしようもないのですが,電気や自動車の世界では,構造や構成をこのように改良した程度ではなかなか特許取得にはつらいものがあります。われわれにはそうした特許の特徴が分かっていましたので,大学では「コア出願方式」という方法を採用しました。書いた特許を「線」の状態でいろいろ改良して,そこから「面」の状態にしていきます。特許を出願後,その改良特許の出願が1年以内であれば,新規性や進歩性が原出願にさかのぼって判断されるという国内優先権制度を利用しました。企業との共同研究でも,同様に完成度を高めて特許にしていく方法を採りました。
聞き手:各大学も同様の考え方なのですか?
虎澤:必ずしもそうではなく,発明委員会というような委員会を設けて,そこで良い特許かどうかを判断し,良くないと判断されたものは出願しないという方法が一般的ではないかと思います。わたしたちは,発明は基本的にすべて出願する方針でやっています。
聞き手:いつも疑問に思うのですが,大学が特許を取る意味はどこにあるといえるのでしょうか?
虎澤:企業ですと,自分たちの事業を守ったり発展させるために特許を取りますので防衛特許も必要ですが,大学は攻撃できる特許じゃないと意味がないですね。要はお金を取れる特許です。他者からお金をもらえる特許とは,自分たちで最先端の研究をし,それを企業と共同研究して企業から収入を得るのが,最高の形態だと考えています。
 ある企業がわれわれの特許を使っていると分かった時に,そこからお金をもらうことは大学の力ではなかなか難しいのではないかと思います。なぜなら,その企業の製品の中身に精通していないといけませんし,法律や裁判にも詳しくなければなりません。しかし,大学はそういうことをするのが目的ではありませんよね。自分たちが研究開発した成果を社会に還元して役立てることが基本的な大学の目的だと思います。ですから,企業と共同研究をして,共同研究先を通じて社会に貢献し,その見返りとして大学が実施料のようなものをいただくということが良い方法と考えています。そしてそれをまた研究に再投資していくのが大学本来の姿だろうと思います。
ある企業がわれわれの特許を使っていると分かった時に,そこからお金をもらうことは大学の力ではなかなか難しいのではないかと思います。なぜなら,その企業の製品の中身に精通していないといけませんし,法律や裁判にも詳しくなければなりません。しかし,大学はそういうことをするのが目的ではありませんよね。自分たちが研究開発した成果を社会に還元して役立てることが基本的な大学の目的だと思います。ですから,企業と共同研究をして,共同研究先を通じて社会に貢献し,その見返りとして大学が実施料のようなものをいただくということが良い方法と考えています。そしてそれをまた研究に再投資していくのが大学本来の姿だろうと思います。

虎澤 研示(とらざわ・けんじ)
1971年,京都大学 理学部卒業。同年,三洋電機?に入社して技術本部開発研究所に配属。1988年,同社 研究開発本部情報通信システム研究所 光技術研究部光記録材料研究室室長。1994年,名古屋大学において博士号取得。1997年,三洋電機 研究開発本部ハイパーメディア研究所 記録メディア研究部部長。1999年,同研究所所長。2004年,三洋電機を退職。同年,名古屋工業大学 テクノイノベーションセンター インキュベーション施設教授。2007年,同大学大学院工学研究科 産学官連携センター知財活用部門グループリーダー兼教授。2011年,同大学退職。同年,名古屋大学 産学官連携推進本部連携推進部 産学官連携コーディネーター(非常勤)。現在に至る。日本応用磁気学会論文賞,日本金属学会技術開発賞,日本貿易振興会感謝状(海外留学生受け入れによる国際貢献)を受賞。








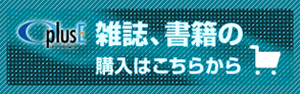
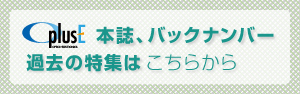

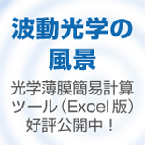







![研究室探訪vol.30 [奈良先端科学技術大学院大学 サイバネティクス・リアリティ工学研究室]](https://www.adcom-media.co.jp/wp-content/themes/adcom/scripts/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2022/11/laboratory1.jpg&w=80&h=100&zc=1&q=100)