小集団的発想こそ日本のオープンイノベーション宇都宮大学 オプティクス教育研究センター コーディネータ 小野 明
日本でもイノベーションは起こせる
聞き手:企業畑でずっとお仕事をやってこられて,あらためて大学の世界に戻り,違和感のようなものは感じましたか?小野:いや,あまり感じませんでした。なぜわたしが企業に入ったかというと,実は父が大学教授だったことに関係しています。父は教授ということもあり,家でずっと勉強していました。そんな時に,子供のわたしが周りで騒いでいると「うるさい,うるさい,外へ行って遊べ」と散々言われた覚えがあります。父のことは尊敬しているし,非常に優しかったのですが,こうした経験から「勉強って嫌だな」と思うようになり,さらに「このまま大学に残るのは嫌だ」と思って,企業に入ったのです。しかし,やはりどこかで親の血が流れているのですね,現在は大学に全く違和感を感じずに過ごしています(笑)。
聞き手:現在のお仕事で特にご興味を持たれているのは,どんなところでしょうか?
小野:今,一番気になっているのは「オープンイノベーション」でしょうか。最近よく聞く言葉ですが,一方で実は日本の企業はみなクローズな体質ですよね。大学もそう簡単には企業と連携できていません。しかし,わたしは,オープンイノベーションは企業と大学の間でやるしかないと思っているのです。
 企業トップ同士が集まっても,その話し合いの場所はせいぜいゴルフ場か料亭くらい。工業会もお互いの様子を見ながら建前をしゃべっているだけ。技術者同士は学会等で同じ分野の人が牽制しあいながら,表面的に話しあうだけです。そうではなくて,ある程度異業種やいる場所の違う人間が互いに顔を合わせてフリーに意見交換ができるような場が必要なのです。その点,大学の先生は,一人一人の専門領域は狭いけれども,「どこどこのだれだれは何をやっている」というような情報を持っていますので,コーディネーターが仲介すれば企業から相談を受けたときに新しい関係をどんどん作ることができます。
企業トップ同士が集まっても,その話し合いの場所はせいぜいゴルフ場か料亭くらい。工業会もお互いの様子を見ながら建前をしゃべっているだけ。技術者同士は学会等で同じ分野の人が牽制しあいながら,表面的に話しあうだけです。そうではなくて,ある程度異業種やいる場所の違う人間が互いに顔を合わせてフリーに意見交換ができるような場が必要なのです。その点,大学の先生は,一人一人の専門領域は狭いけれども,「どこどこのだれだれは何をやっている」というような情報を持っていますので,コーディネーターが仲介すれば企業から相談を受けたときに新しい関係をどんどん作ることができます。よく「日本の企業は垂直統合型が得意」と言われ,「水平統合型をやるとすぐに失敗する」と言われますよね。しかし,いつまでも垂直統合型に依存しているわけにはいきません。それではすぐにオープンイノベーションの世界に移行できるかというと,どうもそうではなさそうです。企業が自らオープンイノベーションに積極的に移行できるかというと,たぶん今の様子ではなかなか難しいと思います。一方で大学がそういう場を提供できれば,わりあいすんなり,仰々しくなく,体力に合ったかたちで何かイノベーションを起こさせるキッカケを作れるのではないかと考えています。
聞き手:日本企業には,そうしたことを拒む体質があるような気がするのですが。
小野:オープンにするためには,「どこからオープンにできる」という企業内共通意識がすごく大切です。そして,主張すべき点を明確にする必要があります。そうすれば,ちゃんとオープンにできるのではないでしょうか。責任者が会議で何を聞かれるか分からないので,ぞろぞろ部下を連れて出席している風景がよくあります。話していいことと話していけないこと,および主張すべき点が明確で,それがちゃんと訓練されていれば,1人でどこにでも出かけられるわけですよ。すると,社外にどんどんオープンな人間関係ができるはずです。
最近,米Apple社のiPhoneやiPadといった製品が何かと話題になりますね。彼らは自分たちで機械を作って,それをオープンにしてアプリケーションなどを第三者に開発させて大きくなってきました。その事業的な発想は,何のことはない,ファミコン時代の任天堂と一緒なのです。Appleのビジネスモデルとは,もともと任天堂の発想だったのじゃないかと思うのです。そのまた源はソニーのウォークマンですし。
聞き手:根っこは,本来,日本の企業が作り上げてきたものと同じですね。
小野:そう。ですから,日本もイノベーションを起そうと思ったら起こせるのです。世界で通用しているシックスシグマなどのMOT手法は,日本の発想から出ていますよね。改善と品質です。日本はそういうものを生み出す力を持っているのです。これらは個人技ではなく小集団的発想なのが海外のやり方と違うところです。一人一人が問題意識を持ち,それを集団の中で話し合っている内に,なんだかイノベーションが起こっていくというやり方です。これはまさに日本的オープンイノベーションなのですね。
聞き手:わたしもメーカーにいたことがありますが,小集団活動のパワーというものは確かにこの目で見ています。
小野:誰か1人がいいアイデアを出しても,残念ながら日本ではそうしたアイデアを潰してしまうケースがよくあります。集団で検討していけば,そういうことは起きません。アイデアが良ければ,それがまた良いアイデアを生み出していきます。それが日本人に向いている一つの方法かなと思っています。
聞き手:さらに企業の垣根を越えて,そうした集まりができるとなると,日本がいろいろと変わっていきそうな気がしますね。
 小野:一方で,企業に研究所を作って,そこに研究者を閉じ込めてしまうのは最悪のことだと思っています。「中央研究所時代の終焉」(Richard S. Rosenbloom,William J. Spencer著,日経BP社刊)という本をご存じですか? 今から10年ぐらい前に結構話題になった本です。その昔,米IBM社や米AT&T社などが中央研究所を作って,ノーベル賞受賞者を輩出していた時代があります。しかし,それらが事業に結びついたケースは皆無に等しいという内容です。そこに自ずから,大学と企業の研究者のすみ分けが見えてきます。現在は,米国ではそういうすみ分けがうまく行きつつあるので,アリゾナ大学やフロリダ中央大学などは,企業のお金を集めて成り立っています。日本企業では,まだ中央研究所を作ってクローズに自分たちだけでやって行くのが良いと考えているので,大学の研究とうまくすみ分けができていません。大学は大学で,「実用化」を目指していますが,スピードの点で企業にどうしても勝てません。
小野:一方で,企業に研究所を作って,そこに研究者を閉じ込めてしまうのは最悪のことだと思っています。「中央研究所時代の終焉」(Richard S. Rosenbloom,William J. Spencer著,日経BP社刊)という本をご存じですか? 今から10年ぐらい前に結構話題になった本です。その昔,米IBM社や米AT&T社などが中央研究所を作って,ノーベル賞受賞者を輩出していた時代があります。しかし,それらが事業に結びついたケースは皆無に等しいという内容です。そこに自ずから,大学と企業の研究者のすみ分けが見えてきます。現在は,米国ではそういうすみ分けがうまく行きつつあるので,アリゾナ大学やフロリダ中央大学などは,企業のお金を集めて成り立っています。日本企業では,まだ中央研究所を作ってクローズに自分たちだけでやって行くのが良いと考えているので,大学の研究とうまくすみ分けができていません。大学は大学で,「実用化」を目指していますが,スピードの点で企業にどうしても勝てません。自分としては偶然なのですが,こうして企業と大学の実態を垣間見れるようになったので,少しは両者のお役に立てるような意見を言えるようになったと思っています。
聞き手:本日は,企業や大学の研究者,開発者のみなさんにとって,大変興味深い話をいただき,ありがとうございました。

小野 明(おの・あきら)
1973年,大阪大学 大学院修士課程精密工学科卒業。同年,株式会社東芝に入社。生産技術研究所に配属。1983年,米アリゾナ大学客員研究員。1988年,大阪大学において工学博士号取得。1996年,東芝 生産技術センター光応用システムセンター長。1997年,技術士(機械部門)取得。1999年,株式会社東芝を定年退職し株式会社トプコンに入社。2000年,同社取締役兼執行役員。2003年,同社取締役兼株式会社トプコンテクノハウス代表取締役社長に就任。2006年,株式会社トプコン 常勤監査役,監査役会議長。2008年,株式会社トプコン顧問。2008年,宇都宮大学 オプティクス教育研究センター コーディネータ。現在に至る。








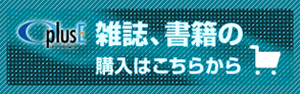
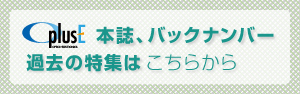

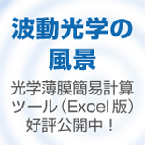







![研究室探訪vol.30 [奈良先端科学技術大学院大学 サイバネティクス・リアリティ工学研究室]](https://www.adcom-media.co.jp/wp-content/themes/adcom/scripts/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2022/11/laboratory1.jpg&w=80&h=100&zc=1&q=100)