着想力が豊かで,実行力が速く失敗を財産とできる前向きな志向の人材を育んでほしいナノサイエンスラボ 代表 門田 和也
発掘力と豊かな着想力があれば,人もお金も後からついてくる
聞き手:アライナーやステッパーと呼ばれるリソグラフィ用の半導体露光装置に関して,ユーザーとして,自社製や, パーキンエルマ社やGCA社などの海外製,国内製それぞれのご使用経験があったとお聞きしています。それぞれに感じたこと等,ヨーロッパ製が強い現状と比較してお話をお聞かせください。門田:半導体は,「論理回路(紙の上のLogic回路)を固体素子(Solid State Deviceチップ)に物理・化学変換をする」ところから始まりましたが,その変換機器は,いわゆる「リソグラフィ技術」です。幸いにも,私は,VLSIの黎明期からこの微細化リソグラフィに関与できました。先人もほとんど居ない状態で,いきなり,トップ集団を走ったのです。
5μm世代までの露光機は,上述した様にコンタクト露光(1:1のネガ型レジスト・プロセス)であり,女性作業員たちが,手動でアライメントし,国内外のファブもこれで構成されていました。
しかし,初期世代のVLSIを開発するとなると,新規に3μm世代の設計とリソグラフィ技術が必要となりました。主な理由は,ネガ型レジストでは,現像中に膨潤を起こし,隣のパターンと接触,スペースが開かなくなる,ドライエッチング耐性が乏しく,プラズマ中で劣化する等々の基本的弱点がありました。また,転写に用いるマスクは,ウエハと100回も“コンタクト“を繰り返すと,ランダム欠陥が発生する上に,アライメント精度が上がらず,設計仕様が未達になるからでした。
これらの弱点を一挙に克服できるのは,プロジェクション(1:1のポジ型レジスト・プロセス;等倍アライナー)でした。マスクとウエハは,約1m離れた構造のため,互いに接触せず,欠陥が入らないため,高精度のオリジナルマスクが1枚あれば,数万枚も露光できました。また,ポジ型レジストは,プラズマ耐性に強いノボラック系を用いたので,設計→露光→エッチ→完成まで,寸法シフトを極めて少なくできました。この一連の方式が,生産技術としてネガからポジへの「パラダイムシフト」となりました。
露光機メーカーとして,米国パーキンエルマ社が世界を席巻していましたが,IBMが協業者として技術をリードしていました。同社は,後にハッブル望遠鏡をNASAに収める等,プロジェクションの実績は偉大でした。その後,国内ではキヤノンが参入,現在に至ります。
しかし,さらにチップを70%シュリンクして,2μm世代に対応するには,重ね合わせ(アライメント)精度が不足しました。そこで登場したのがステッパーです。当時は,露光波長436nm(g-線)で縮小比率10:1 ,NA=0.28の画角,チップサイズ上限は,10mmでしたが,これで±0.5μmの2層間重ね合わせが生産技術として実現できました。生産技術の意味は,年間360日,10~20台のステッパーを休まずフル稼働させ,数万枚のウエハ上で実現できる精度,すなわち,デザインルールとなることを意味します。ただし,難点は,露光処理能力(スループット)が極めて低く,高価なステッパーをファブに大量に並べるのは抵抗もありましたが,設計ニーズに合わせて大型投資を行いました。
 露光機メーカーとしては,1980年代,米国GCA社が世界を席巻したが,この余波で,パーキンエルマ社は凋落して行きました。国内では,ニコン,キヤノンが後続参入し,世界の御三家となりました。
露光機メーカーとしては,1980年代,米国GCA社が世界を席巻したが,この余波で,パーキンエルマ社は凋落して行きました。国内では,ニコン,キヤノンが後続参入し,世界の御三家となりました。その後,半導体の微細化は次々に進み,露光波長は,436nm(g-線)→365nm(i線) →248nm(KrF-レーザー) →193nm(ArF-レーザー)と進化することで,レジスト材料と合わせ,ナノレベルのパターン形成が可能となりました。同時に,チップサイズの拡大に対応して,レンズも4:1縮小,高NA=1.35に変わり,画角サイズも20mm以上が可能となりました。露光時の雰囲気もドライ型から液浸型に進化し,現在では,1層のマスクパターンを2分割,4分割して重ね露光するダブルパターン,クワッドパターンなどで,20nm以下も生産が可能な時代となりました。
ここまでの対応は,特に高精度レンズの設計ができるか否か,まさに「目玉」で決まりましたが,自社でレンズ設計ができないGCAは途中退場となり,逆に,欧州でひっそりしていたASMLが,世界を席巻しはじめました。デザインルール上は,液浸ArFでクワッドパターンを行えば,約10nm世代までは,ナノレベルVLSIが実現できる見通しが得られています。
これ以外のEUV露光技術(波長=13nm)等は,国プロでも取り組みましたが,いまだ完成の見込みも無く,総コストも極めて高額であり,投資しても回収も不可能です。原理上も,液浸ArFを超える優位性は無く,VLSI産業には不要と思われます。野球で言うなら,大飯食いのベンチウォーマで,永久に出番は来ない戦力外のようなものです。
エピソードとしては,365nm(i-線)レンズの開発で紆余曲折がありました。目標は,2μm世代以降を縮小倍率5:1で行ける大口径レンズがどうしても必要でしたが,国内外の露光機メーカーでは開発が遅延しました。NAを大きくし解像性能を上げる一方,露光画角も20mm以上を満たさねばならず,各種の光学収差を低減するために,レンズ設計と製作・調整に2~3年かかりました。試作しては露光テスト,微細パターンをSEMで多点測定し,結果をフィードバックするアナログ的な力仕事でしたが,喧々諤々の議論(協業)を繰り返し,ようやく完成にこぎつけました。
この間,設計側(上流)でできる課題は無いかと考えて思い付いたのが,近接効果補正(OPC)を微細パターンのコーナー部分に配置し,精度を向上し,デザインルールを満たす手法です(p.1219図1右上)。この効果を予測するためには,計算機シミュレーションが必須でしたが,当時は,市販ソフト(EDA)などは無く,すべて自前でソフト開発し,大型計算機をぶん回すしかありませんでした。物理光学のアルゴリズムは存在しましたが,VLSIのパターンに適用する計算事例は無く,2年程度の試行錯誤を経て,実用レベルのソフトが完成しました。これを海外の学会で発表したが,世界初であり,聴衆の度肝を抜き,喝采を浴びました。あの最先端のIBMに勝てたのです。その後,このOPC技術は,各国でEDAツールの実用化が進み,広く世界標準になり,これが無くては,ナノレベルの光露光ができない基幹技術となりました。
もう一つのエピソードは,検査・計測に用いる測長SEM(下流)です。1980年ごろまでは,VLSIのパターン検査,ランダム欠陥検査は,すべて金属顕微鏡で,肉眼による人海戦術しか手段がありませんでした。金属顕微鏡は安くて,カラー情報も得られますが,倍率が1000倍位になると,焦点深度が浅くなり高精度な測定が困難で,長時間の安定測定には目が疲れて耐えられません。
そこで思い付いたのが,電子顕微鏡の採用です。しかし,当時の電子顕微鏡は,科学研究用途であり,像のコントラストを上げるために,表面に金をコートする,真空チャンバーが小さいので,対象のウエハを破断するために,測定後,プロセスに戻せない等々の問題がありました。金の汚染は,VLSIプロセスでは,VLS(蒸気・液体・固体)成長がデバイスを破壊するので,厳しいご法度の材料でした。金コート無しでSEM像を得るには,電子線を低加速電圧(1keV程度)にする必要がありますが,逆に,解像度が極端に低下し,使い物になりません。
私は,電子顕微鏡開発者に,この半導体用途ニーズをぶつけたのですが,すべて,無理難題,矛盾だらけと否定されました。しかし,開発資金を提供するという約束で,要素研究から着手し,紆余曲折を経て,2年後にプロトタイプが完成しました。まだ測長機能や画像処理に不足もありましたが,金属顕微鏡をはるかに凌ぐ性能が得られました。その後,大きな改良を繰り返し,今や,世界標準機まで登り詰めました。
この2例の様に,膨大な情報,データ,現実の山の中からニーズを見つけ,相棒(協業先)を勧誘し,並行して育む,つまりWin-Winするということは,いつの時代でも大切なことです。ニーズに向かって,発掘力と豊かな着想力があれば,人もお金も後からついてきます。 <次ページへ続く>

門田 和也(かどた・かずや)
1943年 神奈川県生まれ 1972年 東京工業大学 大学院理工学研究科 卒業 工学博士 1974年 日立製作所入社 2003年 定年退職後,産総研,東北大学を経て,ナノサイエンスラボ代表●研究分野
半導体設計
●主な活動・受賞歴等
半導体メモリ開発(特に微細加工技術を中心)









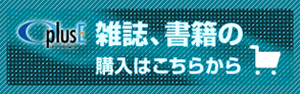
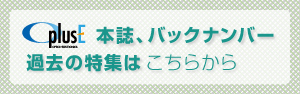

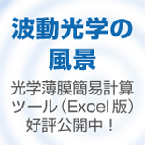







![研究室探訪vol.30 [奈良先端科学技術大学院大学 サイバネティクス・リアリティ工学研究室]](https://www.adcom-media.co.jp/wp-content/themes/adcom/scripts/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2022/11/laboratory1.jpg&w=80&h=100&zc=1&q=100)