第16回 台湾交流録 part 2 予期せぬ展開
HODIC in Taiwan
海外版HODIC(ホログラフィック・ディスプレイ研究会)の例会は,アジアの研究者との交流を目的として立ち上げられており,その第2回が,台湾,新竹のITRI(台湾・工業技術研究院)で2005年12月に開催され,私は参加した。前回の訪問から8年後のことである。新竹は,日本で例えればつくば学園都市のような土地柄で,大学などの教育機関の他,台湾のシリコンバレーとも言われるサイエンスパークのエリアには,研究施設や企業などが集まっている。そのような一角で研究会は開催された。日本からの参加者は交通宿泊費が自前,会議関連についてはすべて台湾サイドの運営という条件であった。1日の講演会は日本と台湾から半々の発表者で構成され,多くの受講者が集まっていた。運営機関から予想される通り,私以外はすべてが技術中心の演題であった。そのためか,プログラムの構成では,私が最終の講演となっていた。さて,出番となり会場を見渡すとそれまで多くの人で埋まっていた座席はいつの間にかガランとしてまばらに人が残っているだけになっていた。「ホログラフィーアートの建築空間への応用」と題して,それまでの私の作品実例の紹介を,ビデオやスライドなどの視覚媒体を中心に発表した。どれほど理解されたかまったく不明で,手応えもなかった。
講演会は無事終了し,夜は台湾流の美味しいおもてなしの晩餐会が催された(図1(a), (b))。ITRIの例会は,HODICの国際担当の岩田藤郎氏(凸版印刷㈱中央研究所)が中心になって企画され計画が進められたのだが,岩田氏から夕食の席でこんなエピソードを聞いた。プログラムの件で,台湾とのやり取りの時,日本からの講演者と演題を知らせたところ,先方から「アート関連の石井の発表は要らない」と言ってきたという。そこで岩田氏は「HODICはHolographic Display Artists and Engineers Clubの略で,アーティストを除くことはできない」と説得し,私の発表を何とか組み込んでもらうのに苦労したということだった。扱いに困り,プログラムの構成に苦慮しての順番だったのであろうが,どうも付け足し感が否めない。ホログラフィーアートは,おそらくITRI界隈ではまったく馴染みのない分野であったのだろう。
 台湾訪問中のメインイベントの1つは,連日催される台湾流晩餐会である。講演会に同行された辻内先生を訪ねて,辻内研の元留学生のDr. Der-Chin Su(国立交通大学教授,前号にも触れた)や,彼の恩師であり辻内先生とは旧知のDr. Yi-Shun Gou(国立交通大学教授)らが,講演会には参加していなかったが,食事会には出席し,共に旧交を温めていた(図2)。その席でGou先生は「いよいよ交通大学を退官だが,師範大学(国立台湾師範大学)の学長選挙に立候補しようと考えている」というようなことを話していた。私は講演の資料,ビデオやホログラムの作品資料を,せっかくの機会なので後で見てもらおうとDr. Suに渡した。それまでの私のアート活動を知ってもらう機会がなかったので,良い機会と思えたからである。宿泊はサイエンスパーク内のドミトリーのような施設で,新竹では自由なショッピングも夜市の散歩もなく,三度目の短い冬の台湾訪問は終わった。
台湾訪問中のメインイベントの1つは,連日催される台湾流晩餐会である。講演会に同行された辻内先生を訪ねて,辻内研の元留学生のDr. Der-Chin Su(国立交通大学教授,前号にも触れた)や,彼の恩師であり辻内先生とは旧知のDr. Yi-Shun Gou(国立交通大学教授)らが,講演会には参加していなかったが,食事会には出席し,共に旧交を温めていた(図2)。その席でGou先生は「いよいよ交通大学を退官だが,師範大学(国立台湾師範大学)の学長選挙に立候補しようと考えている」というようなことを話していた。私は講演の資料,ビデオやホログラムの作品資料を,せっかくの機会なので後で見てもらおうとDr. Suに渡した。それまでの私のアート活動を知ってもらう機会がなかったので,良い機会と思えたからである。宿泊はサイエンスパーク内のドミトリーのような施設で,新竹では自由なショッピングも夜市の散歩もなく,三度目の短い冬の台湾訪問は終わった。
 <次ページへ続く>
<次ページへ続く>











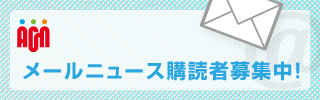
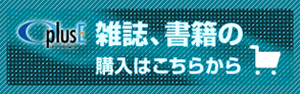
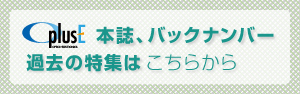
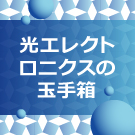
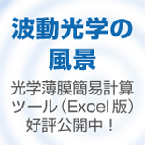



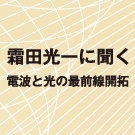
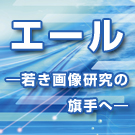


![研究室探訪vol.30 [奈良先端科学技術大学院大学 サイバネティクス・リアリティ工学研究室]](https://www.adcom-media.co.jp/wp-content/themes/adcom/scripts/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2022/11/laboratory1.jpg&w=80&h=100&zc=1&q=100)