複眼カメラTOMBOが実現する高機能デジタルデンタルミラー静岡大学 電子工学研究所 准教授 香川 景一郎
- 説明文
- 写真
複眼カメラTOMBO(Thin Observation Module by Bound Optics)は,大阪大学の谷田純教授により1997年に考案され,1998年から研究が本格的に始まった超小型マルチカメラであり,コンピュテーショナルカメラの先駆けである。昆虫の眼に着想を得て生まれたこのカメラは,クレジットカード大の厚みとサイズをもつ超薄型カメラに留まらず,シート状で曲がるカメラ,欲しい大きさに切って曲面に貼るカメラなど,自由な発想が議論された。当時博士後期課程の学生であった私は夢のカメラに妄想をかきたてられ,木の板を削ってモックアップを作り,こんなカメラにしてほしいのだと研究者たちに説明することもあった。
初期のTOMBOは,レンズが250 μmピッチで2次元的にぎっしりと敷き詰められた平板マイクロレンズアレイをCCDイメージセンサーの上に張り付けた,昆虫の複眼を平面に引き延ばした様なものであった。しかし高画素化・高画質化の要望から,レンズ数は後に3×3個まで減ることになる。 2000年代半ばにはレンズアレイを利用したライトフィールドカメラが注目を集めるようになった。TOMBOはその一種として,シーンを3次元的に捉える超小型カメラとしての側面が強くなり,高精度距離画像計測・超解像の研究が進むが,限界も見えてくる。
2007年中ごろにTOMBOの研究に再び関わるようになった私の興味の中心は,TOMBOの本質は何か,ということであった。1つのイメージセンサー上にレンズを複数並べたこの小さなカメラは,解像度も画質も普通のカメラに劣る画像をいくつも並べて出力する。何年も考えた結果,「TOMBOはとてつもなく小さいマルチカメラだ。TOMBOしか入れない狭い空間,TOMBOしか載れない小さい乗り物(機器)で,対象を一度に多様な方法で見る」ことが特別なのだ,という当然の結論に至った。3次元カメラは一側面に過ぎず,解像度に拘らなくても存在感を示すカメラを創るべきだと考えた。
そこで出来上がったプロトタイプが,写真の口腔観察用カメラである。デンタルミラーの高機能デジタル版であり,歯科医が歯肉の状態を手軽にイメージングする小型分光カメラである。歯肉の腫れを表面の状態によらず計測するためには,構造光投影が有用だろう。形状を直感的に捉えるにはステレオ画像が欲しい。そしてもちろん,苦も無く狭い口の中に入れて自由な視点から見回したい。TOMBOはこれらすべての要求に応える。
TOMBOは考案から20年の歳月を経た歴史ある研究テーマである。しかしいまだに,私が何かを知り,私を使いこなしてみよ,と研究者に問いかけ続ける強敵でもある。その声が聞こえるかどうかは,研究者次第であり,我々の戦いはまだまだ続くのである。
初期のTOMBOは,レンズが250 μmピッチで2次元的にぎっしりと敷き詰められた平板マイクロレンズアレイをCCDイメージセンサーの上に張り付けた,昆虫の複眼を平面に引き延ばした様なものであった。しかし高画素化・高画質化の要望から,レンズ数は後に3×3個まで減ることになる。 2000年代半ばにはレンズアレイを利用したライトフィールドカメラが注目を集めるようになった。TOMBOはその一種として,シーンを3次元的に捉える超小型カメラとしての側面が強くなり,高精度距離画像計測・超解像の研究が進むが,限界も見えてくる。
2007年中ごろにTOMBOの研究に再び関わるようになった私の興味の中心は,TOMBOの本質は何か,ということであった。1つのイメージセンサー上にレンズを複数並べたこの小さなカメラは,解像度も画質も普通のカメラに劣る画像をいくつも並べて出力する。何年も考えた結果,「TOMBOはとてつもなく小さいマルチカメラだ。TOMBOしか入れない狭い空間,TOMBOしか載れない小さい乗り物(機器)で,対象を一度に多様な方法で見る」ことが特別なのだ,という当然の結論に至った。3次元カメラは一側面に過ぎず,解像度に拘らなくても存在感を示すカメラを創るべきだと考えた。
そこで出来上がったプロトタイプが,写真の口腔観察用カメラである。デンタルミラーの高機能デジタル版であり,歯科医が歯肉の状態を手軽にイメージングする小型分光カメラである。歯肉の腫れを表面の状態によらず計測するためには,構造光投影が有用だろう。形状を直感的に捉えるにはステレオ画像が欲しい。そしてもちろん,苦も無く狭い口の中に入れて自由な視点から見回したい。TOMBOはこれらすべての要求に応える。
TOMBOは考案から20年の歳月を経た歴史ある研究テーマである。しかしいまだに,私が何かを知り,私を使いこなしてみよ,と研究者に問いかけ続ける強敵でもある。その声が聞こえるかどうかは,研究者次第であり,我々の戦いはまだまだ続くのである。




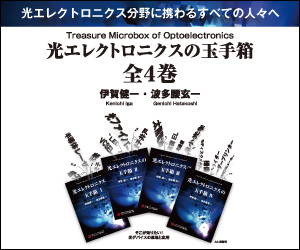







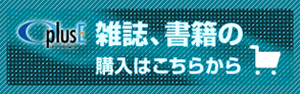
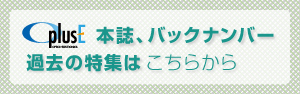

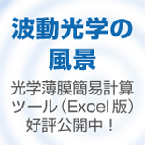







![研究室探訪vol.30 [奈良先端科学技術大学院大学 サイバネティクス・リアリティ工学研究室]](https://www.adcom-media.co.jp/wp-content/themes/adcom/scripts/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2022/11/laboratory1.jpg&w=80&h=100&zc=1&q=100)