研究の醍醐味は未踏の荒野を探し当てること東京大学 工学系研究科 物理工学専攻 教授 香取 秀俊
“わらしべ長者的発想”の実践
聞き手:これまでの研究・開発で行き詰まってしまったものの,試行錯誤された末,最終的に課題や問題を乗り越えられたご経験がありましたらお聞かせください。香取:研究・開発を進めていく上で発生する問題は,いつも次の研究へのヒントとなります。その問題点が四六時中,頭から離れずに考え続けていると,そのうちふとした瞬間に解決するヒントがひらめく時があり,それによって解決できることが1年に数回あります。この数回が,研究に携わる中で私が心から楽しいと実感できるひとときです。研究・開発を進めていく上で起きた課題や問題に対し,必死に取り組んでいる時が,私にとって充実感を味わえるひとときです。
出口の見えないつらさを味わったといえば,MPQでポスドクをしていたころのことですね。MPQでは当時,イオントラップの研究が着々と進められ,私はポスドクとしてその研究に参加したのです。ポスドクは大概,既存のグループ,装置に仲間入りして,その成果を発展させることが期待されます。新しい展開を始めるためには,まずはグループメンバーの説得工作から始めないといけない。いままで,一人で好き勝手にやってきた私にはそんなプロセスが面倒くさくて仕方がなかった。その当時は相当フラストレーションがたまっていました。
 自分の手を動かして自由に研究ができない反面,たくさん考える時間ができました。その時間をイオントラップに関するさまざまな論文を読む時間に充てました。読むことを通じ,これまでイオントラップの研究に携わってきた研究者がまだ考察できていないフィールドを頭の中で整理し,そこから未着手で勝算のありそうな研究テーマの方向性について考えていました。また,偶然にも,隣の研究室で単一イオン光時計を研究していたことも,私にとっては非常に勉強になりました。毎日,私の研究室に通うには必ず隣の研究室の前を通り過ぎるのですが,その度に部屋の壁にあるポスターが目に留まり,その内容が頭の中に記憶として刻まれました。次第にその研究がどうすれば新たな実験ができるかなどを日々考えるようになり,こうした蓄積が光格子時計の研究・開発に着手することにつながっていきました。そもそも,イオントラップでは不可能なことを実現したのが光格子時計であり,こうした発想はイオントラップの研究の限界と困難をよく理解することが根底にあります。
自分の手を動かして自由に研究ができない反面,たくさん考える時間ができました。その時間をイオントラップに関するさまざまな論文を読む時間に充てました。読むことを通じ,これまでイオントラップの研究に携わってきた研究者がまだ考察できていないフィールドを頭の中で整理し,そこから未着手で勝算のありそうな研究テーマの方向性について考えていました。また,偶然にも,隣の研究室で単一イオン光時計を研究していたことも,私にとっては非常に勉強になりました。毎日,私の研究室に通うには必ず隣の研究室の前を通り過ぎるのですが,その度に部屋の壁にあるポスターが目に留まり,その内容が頭の中に記憶として刻まれました。次第にその研究がどうすれば新たな実験ができるかなどを日々考えるようになり,こうした蓄積が光格子時計の研究・開発に着手することにつながっていきました。そもそも,イオントラップでは不可能なことを実現したのが光格子時計であり,こうした発想はイオントラップの研究の限界と困難をよく理解することが根底にあります。今にして思うと,この時期は私にとって一番の“充電期間”であり,このときに得た知識や経験がその後の研究に役立つことになりました。私は,これを“わらしべ長者的発想”と称しています。たとえ研究につまずいても,わらしべ一本ぐらいは手につかむ。どうしようかと真剣に考えていれば,それを有効利用できる次の研究に巡り合う。わらしべ長者よりは,もっと能動的に考えてはいるのですが(笑)。つまり,研究においてもわらをつかんでどんどん歩んで物々交換していくと,自分自身の望んでいたことが実現するということです。 <次ページへ続く>
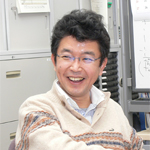
香取 秀俊(かとり・ひでとし)
1964年東京都生まれ。1988年東京大学工学部物理工学科卒業。1991年東京大学工学部教務職員のち同助手,1994年東京大学大学院・論文博士(工学),独マックス・プランク量子光学研究所 客員研究員。1999年東京大学工学部 総合試験所助教授。2010年東京大学大学院工学系研究科物理工学専攻教授,科学技術振興機構・戦略的創造研究推進事業・ERATO香取創造時空プロジェクト研究総括。2011年理化学研究所 香取量子計測研究室 主任研究員(兼務)●研究分野:量子エレクトロニクス
●2005年European Time and Frequency Award,2006年日本IBM科学賞,2008年Rabi Award,2010年市村学術賞特別賞,2011年ジーボルト賞,2012年朝日賞,2013年東レ科学技術賞ほか。










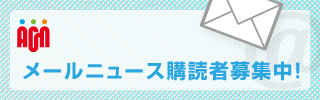
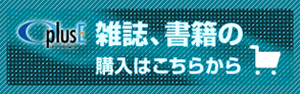
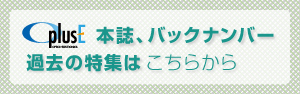
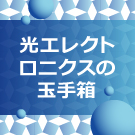
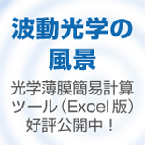



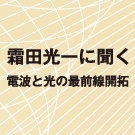
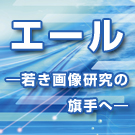


![研究室探訪vol.30 [奈良先端科学技術大学院大学 サイバネティクス・リアリティ工学研究室]](https://www.adcom-media.co.jp/wp-content/themes/adcom/scripts/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2022/11/laboratory1.jpg&w=80&h=100&zc=1&q=100)