日本の光学産業が沈黙した羊の群れのように見える矢部 輝
日本ではレンズ設計の発表件数が光学産業の規模に比べて少ない
聞き手:日本の学会活動と欧米の学会活動に,違いがあればお聞かせください。矢部:単純に言えることはレンズ設計についての日本からの発表件数が光学産業の規模に比べて少ないことです。欧米では各企業の規模が小さいので研究者の間の情報交換の場として学会は重要な役割を果たしていますが,日本では大手企業の内部で情報交換が閉じているというのが私の印象です。例えば私は山路敬三さんの固有収差係数を利用したズームレンズの設計論文が大変に参考になりましたが,山路さんが特許戦略を徹底しキヤノンが急成長してからは参考になるような論文がほとんど出なくなりました。光学産業の外から見るとレンズ設計は成熟した技術で新しいものを開発する必要は何もないように見えてしまいます。しかし技術の進歩のために最初に必要なのは新しい課題を発見することです。課題を共有する場として学会発表を大いに活用してほしいと思います。欧米の学会発表は数は多いですが,技術水準は必ずしも高いとは思えません。昨年,「レンズ設計での人間対機械」というテーマの論文が発表されました。アメリカでレンズ設計の名人として有名な設計者の設計と自動設計ソフトの設計を比較するという企画で,昨年,日本でプロ棋士と将棋ソフトが対局したのと似たようなものです。結果は名人がわずかに勝利し両者が互いをほめたたえて終わっているのですが,私がその問題を自分で解いてみたところ,非常に簡単で私のグローバル最適化で3個目の解がすでに名人の解より良い性能で,計算時間は1分もかかりませんでした。名人がその解を求めるのに大変な努力をしたということが私にはどうにも理解できません。
 2007年にフォーブズ氏が直交函数系による非球面形状の表現を発表して以来,それを使うと最適化の効率が非常に高くなると欧米でもてはやされています。私にはこの現象も非常に奇異に見えます。1980年代に私が最初に非球面による設計を試みた時,単項式の係数をそのまま独立変数にするのでは最適化の効率が悪いのはすぐにわかりました。そして適当な変数変換を行なうと最適化の効率が飛躍的に向上することを発見し,非球面の設計でずっと利用してきました。直交函数系を使うと最適化の効率が高まると感動した設計者は,何十年も単項式の係数で漫然と設計してきたのでしょうか。そして非球面形状の初期値を上手に設定することがレンズ設計者の才能であると思っていたのでしょうか。変数変換の方法にはいろいろな可能性があり,フォーブズ氏は二つの方法を提案しましたが,私が使っていたのは別の方法で厳密な直交関係はありませんでした。2006年に非球面形状の製造誤差感度を設計段階で制御する方法を私が発表した時には,フォーブズ氏が提案した直交多項式の一つと同じものを使っていました。これは「フォーブズ多項式」という名称を使いたかった人々には残念だったようですが,1985年にベルリン工科大学のクロース氏とシューマン氏がドイツ語の学会誌で同じものをすでに発表していたことが最近になってわかり,彼らもあきらめがついたようです。このためではないと思いますが,フォーブズ氏は現在はもう一つのより複雑な直交函数系の普及に力を注いでいます。フォーブズ氏は私と同年代ですが,1980年代の初期から非常に質の高い論文を発表し続けている優秀な学者です。1998年以来,彼とは学会で会うたびに話をしてきましたが,彼の言葉は隅々まで聞き取れますし,私は自分の話したい言葉が次々と頭に浮かんできて,普通より1.5倍くらい早く話すことができます。とても誠実な人柄で,彼の言葉が私に聞き取りやすいのは日本人を相手に発音や言葉使いに気を使っているからだと思います。私とフォーブズ氏の性格の最大の違いは,単純な方法と複雑な方法が選べる場合に,私は単純な方を選び彼は複雑な方を選ぶということです。1990年代の初期に彼はASA(Augmented Simulated Annealing)というグローバル最適化方法を開発しました。その方法を解説する彼の論文は100ページくらいあって,中身は函数論的な式で埋め尽くされています。ASAはOSLOに実装されているのですが,OSLOの開発者のダグラス・シンクレア氏が「わからないからあげる」と一色先生にくれたものを,さらに私がもらって読みました。私にとっては読んで楽しい式の展開で最後まで読んだのですが,私は「こんなものを誰がプログラミングするか」と思いました。
2007年にフォーブズ氏が直交函数系による非球面形状の表現を発表して以来,それを使うと最適化の効率が非常に高くなると欧米でもてはやされています。私にはこの現象も非常に奇異に見えます。1980年代に私が最初に非球面による設計を試みた時,単項式の係数をそのまま独立変数にするのでは最適化の効率が悪いのはすぐにわかりました。そして適当な変数変換を行なうと最適化の効率が飛躍的に向上することを発見し,非球面の設計でずっと利用してきました。直交函数系を使うと最適化の効率が高まると感動した設計者は,何十年も単項式の係数で漫然と設計してきたのでしょうか。そして非球面形状の初期値を上手に設定することがレンズ設計者の才能であると思っていたのでしょうか。変数変換の方法にはいろいろな可能性があり,フォーブズ氏は二つの方法を提案しましたが,私が使っていたのは別の方法で厳密な直交関係はありませんでした。2006年に非球面形状の製造誤差感度を設計段階で制御する方法を私が発表した時には,フォーブズ氏が提案した直交多項式の一つと同じものを使っていました。これは「フォーブズ多項式」という名称を使いたかった人々には残念だったようですが,1985年にベルリン工科大学のクロース氏とシューマン氏がドイツ語の学会誌で同じものをすでに発表していたことが最近になってわかり,彼らもあきらめがついたようです。このためではないと思いますが,フォーブズ氏は現在はもう一つのより複雑な直交函数系の普及に力を注いでいます。フォーブズ氏は私と同年代ですが,1980年代の初期から非常に質の高い論文を発表し続けている優秀な学者です。1998年以来,彼とは学会で会うたびに話をしてきましたが,彼の言葉は隅々まで聞き取れますし,私は自分の話したい言葉が次々と頭に浮かんできて,普通より1.5倍くらい早く話すことができます。とても誠実な人柄で,彼の言葉が私に聞き取りやすいのは日本人を相手に発音や言葉使いに気を使っているからだと思います。私とフォーブズ氏の性格の最大の違いは,単純な方法と複雑な方法が選べる場合に,私は単純な方を選び彼は複雑な方を選ぶということです。1990年代の初期に彼はASA(Augmented Simulated Annealing)というグローバル最適化方法を開発しました。その方法を解説する彼の論文は100ページくらいあって,中身は函数論的な式で埋め尽くされています。ASAはOSLOに実装されているのですが,OSLOの開発者のダグラス・シンクレア氏が「わからないからあげる」と一色先生にくれたものを,さらに私がもらって読みました。私にとっては読んで楽しい式の展開で最後まで読んだのですが,私は「こんなものを誰がプログラミングするか」と思いました。欧米では今,産学共同で自由曲面の設計,製造,測定方法の開発に力を入れています。2012年にフォーブズ氏は自由曲面のための直交函数系を発表しましたが,それは非球面の表現方法のうちの複雑な方,つまり私やシューマン氏が考えたのとは別の方を自由曲面に拡張したものでした。私はその論文を読んだ時に,「こんな面倒なものを業界標準にされてはかなわない」と思って,シューマン氏の表現を自由曲面に拡張したものをすぐに論文発表しました。つまり世界の光学産業に対して一つの選択肢を提供したわけです。このテーマに対して私は日本からの発信に出会ったことがありません。欧米の動きを座視し,彼らの決定にすべて任せるつもりのように見えます。今回のODF’14でヴィリー・ウルリッヒ氏が光学産業での標準化とカール・ツァイスでの自由曲面設計の進歩について同時に発表しました。ウルリッヒ氏とは2002年からの知り合いで,ドイツに住んでからもお世話になりました。今はツァイスの光学技術の元締めという立場です。ツァイスではDLS(Damped Least Squares)を改良して自由曲面設計の効率が向上したという発表でしたが,彼らはなぜ1970年代に同じ改良ができなかったのでしょうか。今ごろになってできたと言うのは,かえって恥ずかしい話ではないでしょうか。非球面形状の独立変数の選び方に何の工夫もしてこなかったのと同様です。この程度の技術水準のグループに標準化の方向を任せるというのは危ういことだと私は思います。
私には日本の光学産業が沈黙した羊の群れのように見えます。私がハワイの学会に参加した時,大手の企業は数人単位で参加していましたが,その方々はやはりいつも群れていました。私がその学会で居心地の良さを感じたのは,欧米から参加者が皆一匹狼だったからだと思います。私はその時,自分の仲間に初めて出会いました。私は羊に向かって「狼に生まれ変われ」とも「狼の真似をしろ」とも言うつもりはありません。ですからどうすれば良いかは簡単ではありません。今,日本の光学産業も産業全体も長期の経済の停滞と厳しい国際競争に苦しんでいますが,私は日本社会の対応に何か根本的な視点が欠けている気がします。規制緩和と自由競争による経済の活性化というのは欧米風のいわば狼の論理ですが,日本にそれを当てはめても日本で狼が増えるわけではなく,弱い羊が切り捨てられるだけです。
私は大学で物理学を勉強しましたが,今の日本の状況を見ていると経済学を勉強していた方が世の中の役に立てたかもしれないと思っています。伊藤元重さんは東大オーケストラのトロンボーン奏者の2年先輩で何回か一緒に演奏会に出ました。彼は練習の合間にもコルモゴロフの函数解析学などを読んでいて,こんな優秀な人が経済学を勉強するのはもったいないと私は内心思っていました。しかし経済学を選んだのは彼の優秀さのまさに証拠でした。国部毅さんは浦和高校の同級生で,地理の自由研究で,当時の浦和市内の土地利用を調べるという4人のグループで一緒でした。4人で手分けをして1ヶ月くらいかけて放課後に自転車で市内を走り回って白地図に土地利用の色を塗っていきましたが,そのころはずいぶんヒマだったようです。日本の国債残高の大きさが問題になっていますが,国債残高と国民の貯蓄額は同じ程度です。国債残高がなくなった時,国民の貯蓄も同時になくなるかもしれません。大学を卒業してから彼には会っていませんが,私の素朴な疑問に彼はわかりやすく答えてくれるでしょうか。
私は今後は日本を拠点として仕事をしたいと思っています。狼も羊の真似はできませんが,仲間としてよろしくお願いいたします。

矢部 輝(やべ・あきら)
1953年岩手県生まれ 1978年東京大学物理学科卒業 1978年富士写真光機入社2003年富士写真光機退職 現在は,独立のレンズ設計者として活動
●研究分野
応用光学,光学設計



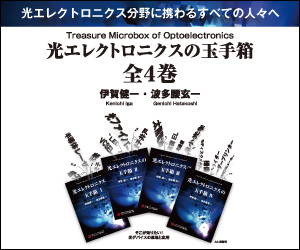







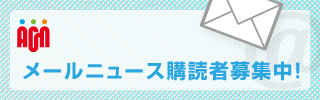
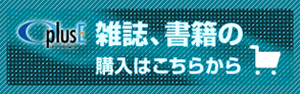
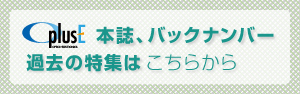
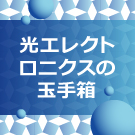
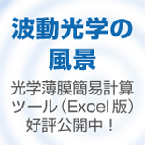



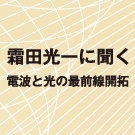
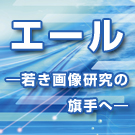


![研究室探訪vol.30 [奈良先端科学技術大学院大学 サイバネティクス・リアリティ工学研究室]](https://www.adcom-media.co.jp/wp-content/themes/adcom/scripts/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2022/11/laboratory1.jpg&w=80&h=100&zc=1&q=100)